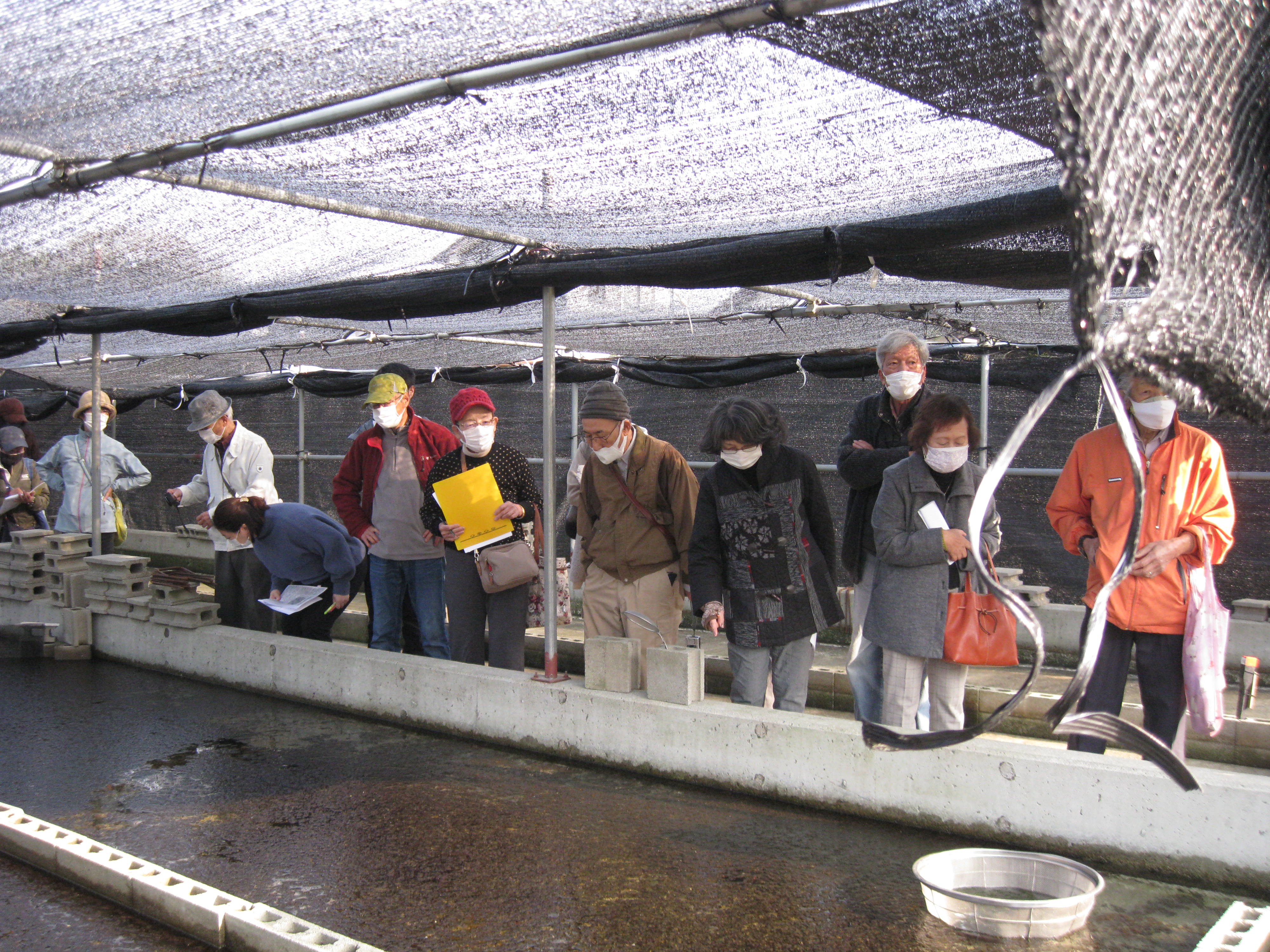令和6年10月19日と11月30に「漱石ゆかりの地を訪ねて」秋のフットパスを開催しました。漱石を訪ねるイベントは去年の秋に2回、今年の秋に2回、合計4回の開催になります。10月は大変な天気で終わるころには雷もなりだしました。カミナリは危険ですので、ゴール地点まで行かずに途中で終わりました。

11月30日は大変に良い天気で、フットパスには最高の日和でした。さて、夏目漱石は明治29年4月第五高等学校の英語教師として赴任しました。熊本では明治33年7月まで暮らしました。熊本で4年3カ月くらしたことになります。漱石は小説家として、大変に有名ですが、熊本時代は小説は書かずに、コツコツと俳句を詠んでいます。いろいろな所に旅をして、その場所場所で多くの俳句を詠んでいます。熊本時代に約1000句をつくりました。

この家は、現在、水前寺公園の東隣りにあります。元々は大江にあったもので、「大江の家」と呼ばれています。漱石と同僚の山川は明治30年の暮れから河内方面の小天に旅をしました。小天の宿には聡明で綺麗な女性がいました。後に小説「草枕」にしています。前田つなさんは魅力的な女性に見えたのでしょうか。小説では那美として登場させています。

この建物は、ジェーンズ邸といいます。元々は県立第一高校の敷地にありました。熊本地震前は「大江の家」の東隣りにありました。地震で滅茶苦茶にこわれました。熊本地震は夜でしたので、この建物での人的被害はありませんでした。新しいジェーンズ邸は水前寺公園の南隣りに建設されています。

 暑かったので、できるだけ木陰で説明した。4月も5月も全く同じコース。動植物園の正面入口をスタートして、ゴールは県立図書館付近である。このコースは下江津湖→中江津湖→上江津湖→県立図書館付近でゴール
暑かったので、できるだけ木陰で説明した。4月も5月も全く同じコース。動植物園の正面入口をスタートして、ゴールは県立図書館付近である。このコースは下江津湖→中江津湖→上江津湖→県立図書館付近でゴール 水前寺江津湖公園の広さは約126haで熊本城(98ha)よりかなり広い。加勢川の上流から下流に公園が出来ている。いちばん上流が北の現在ジェンズ邸がある水前寺地区で、一番下流がサービスセンターがある広木地区である。ジェンズ邸からサービスセンターまで約5キロある。公園は大変に広いので6つの地区に分かれている。上流の北から(水前寺地区、出水地区、上江津地区、下江津地区、庄口地区、広木地区)である。
水前寺江津湖公園の広さは約126haで熊本城(98ha)よりかなり広い。加勢川の上流から下流に公園が出来ている。いちばん上流が北の現在ジェンズ邸がある水前寺地区で、一番下流がサービスセンターがある広木地区である。ジェンズ邸からサービスセンターまで約5キロある。公園は大変に広いので6つの地区に分かれている。上流の北から(水前寺地区、出水地区、上江津地区、下江津地区、庄口地区、広木地区)である。 5月25日の上江津湖にはアメリカデイゴ(カイコウズ)が今を盛りに咲いていた。地球温暖化で5月もかなり暑い日がある。歩くときは暑さ対策も大切である。主催者としては、暑い日のイベントは細心の気配り、目配りをする必要がある。
5月25日の上江津湖にはアメリカデイゴ(カイコウズ)が今を盛りに咲いていた。地球温暖化で5月もかなり暑い日がある。歩くときは暑さ対策も大切である。主催者としては、暑い日のイベントは細心の気配り、目配りをする必要がある。




 漱石は生涯に2600あまりの俳句をつくっています。熊本時代に約1000句つくりました。2600句のなかで一番の秀作は、ここ水前寺成趣園にあります。
漱石は生涯に2600あまりの俳句をつくっています。熊本時代に約1000句つくりました。2600句のなかで一番の秀作は、ここ水前寺成趣園にあります。 漱石は芭蕉が大好きだったようで、芭蕉の句を多く詠んでいます。驚くことには、最後の北千反畑町の第六旧居には今でも芭蕉があります。高浜虚子の「縦横に水の流れや芭蕉林」の句碑もここにあります。
漱石は芭蕉が大好きだったようで、芭蕉の句を多く詠んでいます。驚くことには、最後の北千反畑町の第六旧居には今でも芭蕉があります。高浜虚子の「縦横に水の流れや芭蕉林」の句碑もここにあります。 毎回、大変に参加者が多いですので、早めの申込をお願い致します。上の写真は県立図書館の南隣り、芭蕉園です。夏の芭蕉には、生きるエネルギーをもらえます。
毎回、大変に参加者が多いですので、早めの申込をお願い致します。上の写真は県立図書館の南隣り、芭蕉園です。夏の芭蕉には、生きるエネルギーをもらえます。